年金改正法案が2025年6月13日に可決し、ボーナス込みで年収1000万円以上の会社員や公務員などを対象に、保険料の上限が引き上げられることが決定しました。
この変更は一見「高所得者だけの話」と捉えられがちですが、実は40代を中心とする多くの世代にとって、老後設計や今後の収入計画に大きな影響を与える可能性があります。
本記事では制度変更の全容とその背景、保険料や年金額への具体的な影響、そして老後に向けた現実的な対応策について詳しく解説します。
また簡単副業としてアンケート調査におすすめの大手企業3社を紹介し、それぞれの特徴やメリットをわかりやすく説明しましょう。
制度改正のポイント|何がどう変わるのか?

引き上げ開始は、2027年9月を予定し段階的に施行される制度変更では、標準報酬月額の上限が65万円から最大75万円に引き上げられます。
年収1000万円以上が対象に
これまで、標準報酬月額65万円(ボーナス込みで年収およそ1000万円相当)以上の層は、それ以上稼いでも厚生年金の保険料は一律でした。
しかし2027年からは、以下のように段階的に上限が引き上げられます:
第1段階(2027年9月):65万円 → 68万円(第33級新設)
第2段階(2028年9月):68万円 → 71万円(第34級新設)
第3段階(2029年9月):71万円 → 75万円(第35級新設)
この変更により、月収75万円を超える高所得層も追加で保険料を納める必要が生じます。
これは高所得層の厚生年金納付額を実態に即して見直し、制度全体の公平性と財源安定を図る動きの一環です。
増額される保険料のシミュレーション
現在の最高保険料は月額約59,475円(本人負担)ですが、上限が75万円に達すると月額68,625円にまで増加します。
年間で換算すると約110,000円の負担増となり、家計に与える影響は無視できません。
特に40代でボーナス込みで年収が900万円台の方は、今後の昇給や転職などで対象になる可能性が高く、自身の収入設計に照らして検討することが必要です。
引用元:東洋経済
上限引き上げは損か得か?年金額の増減を検証

「支払う保険料が増えるなら、その分年金も増えるのでは?」という疑問に答えるため、受給額への影響を解説します。
受け取れる年金額は増えるが“限界あり”
厚生年金は報酬比例部分が加算される仕組みのため、保険料の増加は年金額の増加に繋がります。
ただし、現実には掛けた金額に対して“満額回収”できる人は一部に限られます。
- 平均寿命まで受給し続けた場合でも、回収率は約80~90%程度に留まる
- 早期退職、死亡、離婚、配偶者の扶養状況などによって受給年数が短くなり、結果的に負担に見合わないケースも多い
また将来の制度改正リスクやインフレの影響も無視できず、「払った分だけ得をする」とは限らない現実があります。
単純な「支払額=受取額」ではなく、リスクやライフステージに応じた見極めが求められます。
40代が特に気をつけたい「負担とリターンの差」
40代で年収1000万円前後の場合、この制度改正はまさに“自分が該当するかも”という境界線です。
昇進や転職、企業の評価制度の変更などによって、いつの間にか標準報酬月額が上限を超える可能性も高くなります。
このときに重要なのは「支払った分だけリターンが得られるか」という視点だけでなく、「手取りがどれだけ減るか」「他の投資機会を失わないか」など、総合的に判断することです。
特に教育費や住宅ローンの支出が重なる世代にとって、月1万円の手取り減少は生活設計に影響を与える可能性があります。
今後年収が増える見込みがある人は、予め自分がどの等級に該当するのかを把握し、必要に応じて社労士やファイナンシャルプランナーと相談しておくのが得策です。
手取りが減る?老後資金設計の見直しが必要

標準報酬月額の上限が上がることで、毎月の手取りが目減りするのは避けられません。
この影響は老後資金だけでなく、日々の生活や貯金計画にも波及します。
社会保険料控除で節税にはなるが…
厚生年金保険料は社会保険料控除の対象となるため、納付額に応じて所得税・住民税の軽減効果があります。
たとえば年収1200万円で保険料が年間11万円増えた場合でも、その一部が税控除されることで、実質的な負担は月あたり6000円前後にとどまるという試算もあります。
とはいえ実際の可処分所得は減ることに変わりはありません。
住宅ローンや子どもの教育費など40代は支出の多い世代でもあるため、このような“見えにくい”負担増が日常生活や資産形成に与える影響は小さくないのです。
控除だけに期待せず、家計全体での見直しが求められます。
iDeCo・NISAとのバランス再考を
手取りが減少する状況下で、老後のための資産形成手段を厚生年金だけに頼るのはリスクがあります。
特にiDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISAの非課税制度は、民間ベースでの自助努力を促す制度として注目されています。
iDeCoは掛け金が全額所得控除の対象になり、老後資金の形成と節税の両方が可能です。
一方新NISAは運用益が非課税となる点で、投資初心者にも扱いやすい制度です。
これらを活用することで厚生年金の保険料増に対応しつつ、自分のペースで将来に備えることができます。
特に40代はリタイアまでの時間がまだあるため、早めの準備が“差”となって将来表れます。
給与明細や可処分所得を定期的に見直し、適切な資産配分と制度活用を心がけることが、これからの時代の必須スキルといえるでしょう。
なぜ引き上げ?制度変更の背景と国の狙い

この制度変更の裏には、少子高齢化と年金財源の持続可能性という大きな課題があります。
財源確保のための“高所得者ターゲット”
上限引き上げによって保険料収入が増加すれば、年金財源の安定化が見込まれます。
対象となるのは全体の6.5%程度の高所得層で、広く薄くではなく“厚く狭く”負担を求める形です。
これにより年金制度全体の持続可能性を高め、将来的な給付水準を維持することが狙いとされています。
また少子化による労働人口の減少で、現役世代の保険料収入が頭打ちとなる中、より多く稼ぐ層に負担を求めることで全体の収支バランスを保つという現実的な施策ともいえます。
健康保険とのバランス調整も目的のひとつ
現行制度では健康保険の等級上限がすでに月収139万円と非常に高く設定されているのに対し、厚生年金の上限が65万円に留まっていたため、両者の間に大きな差が生じていました。
この“制度間のアンバランス”を解消するためにも、厚生年金側の等級引き上げは避けて通れなかったのです。
健康保険と厚生年金の仕組みを整合させることで、制度全体の合理性と公平性を担保するという観点も、今回の改正の背景にあります。
厚生年金保険と健康保険は同じく標準報酬月額を基準としていますが、下表のように上限額に大きな差が生じています。
この格差も上限見直しが議論される理由の一つです。
| 平成16年10月~ | 平成19年4月~ | 平成28年4月~ | 令和2年9月~ | |
| 健康保険の上限等級の額 | 98万円 | 121万円 | 139万円 | |
| 厚生年金保険の上限等級の額 | 62万円 | 65万円 | ||
※現在、健康保険上限額(139万円)と厚生年金保険の上限額(65万円)には74万円の差があります。
働き方やライフプランへの影響は?

年収900万円台の人は、昇給によって制度の影響を受ける“予備軍”です。
ライフステージに応じて柔軟な戦略が必要です。
昇給・転職時に「上限入り」を意識
40代で管理職への昇進や転職によって年収が1000万円を超えるケースは多いでしょう。
この場合厚生年金の高等級に該当する可能性があり、保険料の負担が増えることになります。
そのためキャリアアップや転職を考える際には、給与の額面だけでなく“実質の手取り”や“将来的な年金受給額”まで考慮することが重要です。
また昇給やインセンティブ報酬などにより、年収が変動しやすい職種の方は特に注意が必要です。
月収が68万円・71万円・75万円と段階的に引き上げられる新しい基準を念頭に、自分がどのラインで影響を受けるかを常に意識しておくことで、想定外の負担増を防ぐことができます。
自営業との格差も再考の材料に
自営業やフリーランスなど国民年金のみ加入の働き方をしている人との比較も、将来のライフプランを立てるうえで重要な視点です。
国民年金の支給額は年間で約80万円前後(満額の場合)に対し、厚生年金は平均で年金支給額が約150万円〜200万円台と倍以上の差が出ることもあります。
一方で厚生年金加入者は保険料の負担も重く、上限引き上げによりさらなる支出が発生します。
自営業は年金額が少ない反面、保険料の自由度が高く、iDeCoや民間保険を活用した資産形成の裁量が広がるというメリットもあるのです。
そのため転職や副業を含む働き方の選択肢を広げる際には、単なる収入額だけでなく「将来の受給額と負担のバランス」を重視した意思決定が求められます。
今からできる現実的な対策5選

厚生年金の上限引き上げは「高所得者向けの変更」と思われがちですが、40代にとってはまさに今から対策すべきライフイベントです。
将来的な年収アップや生活の変化に備え、今できる現実的なアクションを5つ紹介します。
年収が上限に届くかの確認と試算
まず最初に取り組むべきは、自分の収入が将来的に制度変更の対象になるかを把握することです。
厚生年金の保険料は「標準報酬月額」で決まり、これは月収と賞与を元に算出されます。
たとえば年収900万円台でも、賞与が年200万円を超えると上限に近づく可能性があります。
自分の標準報酬月額が現在どの等級にあるのか、そして昇給や転職によってどこまで上がり得るかを一度試算してみましょう。
企業の人事担当や社労士に相談すれば、将来のシミュレーションも可能です。
今後の収入変動を踏まえて、保険料負担と受給見込みをバランスよく見直すのが得策です。
手取り減への備えとして支出の見直し
保険料の上昇は、可処分所得(手取り収入)の減少に直結します。
対策としては、まず固定費を見直すこと。
特に40代で多いのが、住宅ローン・子どもの教育費・生命保険料などの長期支出です。
たとえば変動金利から固定金利への借り換えや、子どもの塾代・習い事のコスト調整も有効な手段です。
加えて生命保険や医療保険も必要以上に重複していないか確認しましょう。
生活の質を落とさずに支出をコントロールする方法を考えることで、毎月の家計に余白が生まれます。
収入が増えても手取りが減るなら、そのぶんをどこで調整するかを“戦略的に”設計することが求められます。
iDeCo・企業型DCの拠出枠最大活用
老後資金を自力で積み立てる手段として注目されているのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)です。
これらは掛金が全額所得控除となるうえ、運用益も非課税という大きなメリットがあります。
特に厚生年金の保険料が上がることで「支払うだけで終わる」という不安がある人にとって、iDeCoなどの積立は“自分でコントロールできる年金”としての価値が高まります。
上限拡大により手取りが減る分、節税しつつ老後資産を形成できる仕組みを活用することが、将来の安心に直結するでしょう。
職場で企業型DCに加入している人は、マッチング拠出制度も含めて最大限活用できるよう再確認を。
新NISAや積立投資で資産分散
新NISA制度の拡充により、つみたて投資の税制優遇枠が拡大されました。
これは厚生年金への依存度を下げ、老後資産の“第二の柱”として機能させる有力な手段です。
積立型のNISAは、月数万円から始められるうえ、運用益が非課税であるため、長期保有によって複利の効果を得やすくなります。
保険料の増額によって資産形成が遅れる不安を、新NISAの活用で補う戦略は非常に現実的です。
特に40代は運用期間を20年以上確保できる最後のチャンスともいえる時期。
リスクを抑えつつも資産を分散し、安定的な老後資金の形成に取り組むことが重要です。
配偶者や扶養の調整も視野に
世帯全体で見た場合、配偶者の働き方や扶養の調整によっても保険料負担は変わってきます。
たとえば夫婦ともに厚生年金加入者である場合、一方が上限に達するなら、もう一方の収入を“扶養内”に抑えることで、世帯全体の社会保険料をコントロールできる可能性があります。
また専業主婦(第3号被保険者)と比較しても、短時間労働のパートであっても第2号として厚生年金に加入できる場合もあるため、働き方の選択は多角的に検討すべきです。
今後子育てが一段落するタイミングや、介護などの事情が発生したときこそ、世帯年収と保険料負担のバランスを見直すチャンスです。
主婦がアンケート調査で副業を始めるなら?初心者にもおすすめの企業3選

副業が当たり前になりつつある今、スマホ1つで始められるアンケート調査が注目されています。
中でも信頼性が高く安心して利用できる企業に登録することが、継続して稼ぐための第一歩です。
アンケート副業におすすめの大手企業は、次の会社です。
- 株式会社ネオマーケティング:高単価調査とモニター案件が魅力
- イプソス株式会社:世界最大級のグローバル調査企業
- 株式会社マクロミル:国内最大級のアンケートモニターサイト
私の関連記事「専業主婦がアンケート調査で副業を始めるなら?初心者にもおすすめの企業3選」で詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ|制度を「知って動く」が差をつける
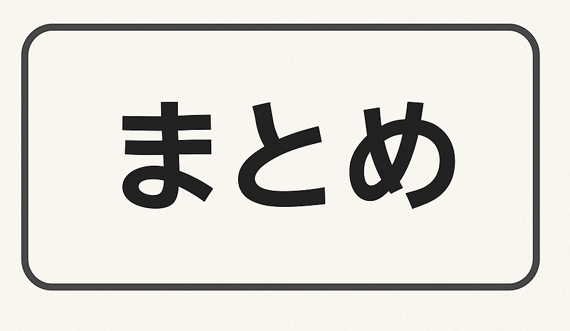
厚生年金の上限引き上げは、高所得層だけでなく「これから上限に届く可能性がある人」にとっても他人事ではありません。
支払いが増えるからといって「損」だと決めつけるのではなく、その分をどう受け取りに変えるか、あるいは別の制度で補うかの戦略が求められます。
老後資金に直結するからこそ、情報を得て、自分に合った備えを早めに始めていきましょう。

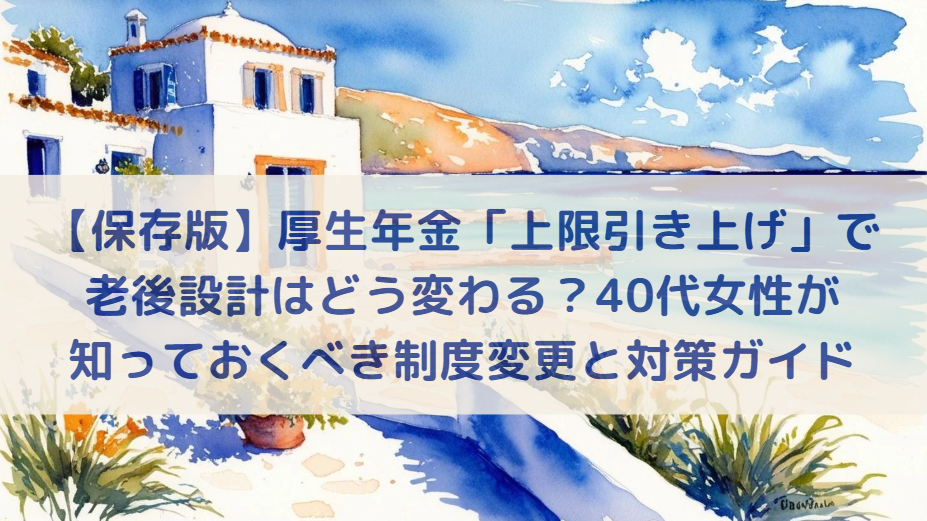
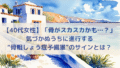
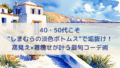
コメント